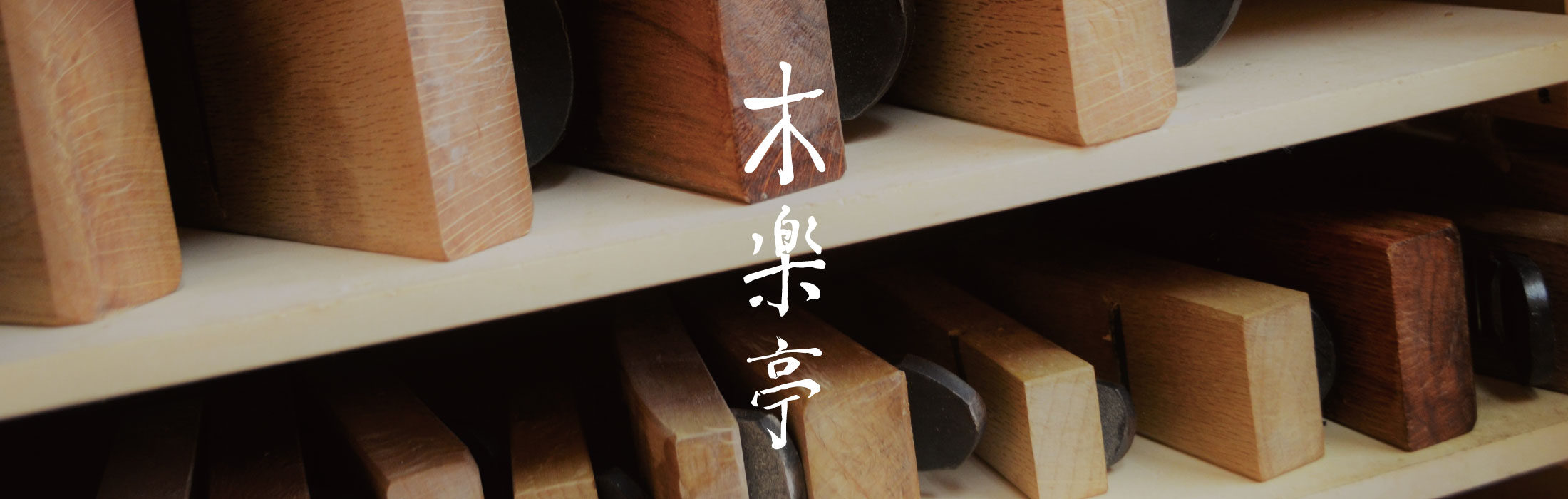馬鹿チョンカメラのSDカードが劣化して、写真がパーになったので、暫く更新できませんでした。

本体の組み立てを終わってからは、細かい作業の連続なんですが、写真は欄干の塗装を終わって所定位置にセットした様子です。 全て着脱可能になっています。左サイド上には扉2枚と背板が揃いました。

右ウイングです。

続いて左ウイング。 ここまでくればあと一歩です。華奢な構造で心配しましたが、組み上がると意外にしっかりしています。

ずっと悩んでいた天板ですが、組立てに漕ぎつけました。最初18mm厚ぐらいの矧ぎ板にしようと思っていましたが、全体の重量に対して余りにトップヘビーになるので、ここも框構造にしました。

天板が出来ました。塗装前ですが大体こんな感じの収まりです。左右の筆返しモドキみたいな形状が難しかったです。加工法やら工程手順が複雑で、逐一写真を撮りながらUPしたかったのに、残念です。

残った写真はこれだけ。右の3枚は、所謂畳摺りです。縦方向の柱6本は20mm角なので、そのままでは畳を痛めてしまいます。畳の養生の為にスキー板みたいな畳摺りをあてがいます。
左のずんぐりした部材が、天板両サイドの「筆返しモドキ」の材料です。
上側は部材の状態で加工し、天板本体に接着した後下側の加工に入ります。下側も部材での加工が容易ですが、そうするとクランプできません。

いきなりですが、こういう風になります。
扉の吊り込みも完了。記憶に間違いがなければ、一発で決まったのは初めてです。気分を良くしてたばこを吸いながら眺めていて愕然!
何と扉の引手を付けるのを忘れていました。不自由な態勢で何とかやっつけてやりました。
今回も長かったですけれども、ようやく完成間近です。あと2日かな?
完成したら所定位置に置いて撮影・報告します。

2枚目の写真にあった籠ですが、「清風籠」って言います。
専攻している「網代」の一種なんですが、ちょっと今までのとは趣が違うんです。 本来は茶道で炭籠として使われるらしいんですが、ちょっと引き付けられてしまいました。

全体としては網代の繊細で端正な雰囲気なんですが、どことなく野趣があるんです。
よく観察すると
1. 普通は剥がしてしまう表面のWAX層をそのままにしてある。(この層があると後で染める事が出来ない。つまり、染めなくて良いという発想。)
2. 網代ヒゴは普通厚0.25mmで使うが、0.4mmという厚みになっている。
3. ヒゴの表側の面取りがされていない。
4. 節部分は網代の場合表面の出っ張りを削るが、敢えて削っていない。従って節部分の凹凸がそのまま見えている。
節部分の厚みは1mm以上あり、これがあることで繊細な網代に野趣を添える重要なポイントになっている。

ということで編み始めました。
簡単そうに見えていましたが、やってみるとトンデモなく厄介なことが解ってきましたが、それはまあ、別に報告いたしましょう。
今日はこの辺で。