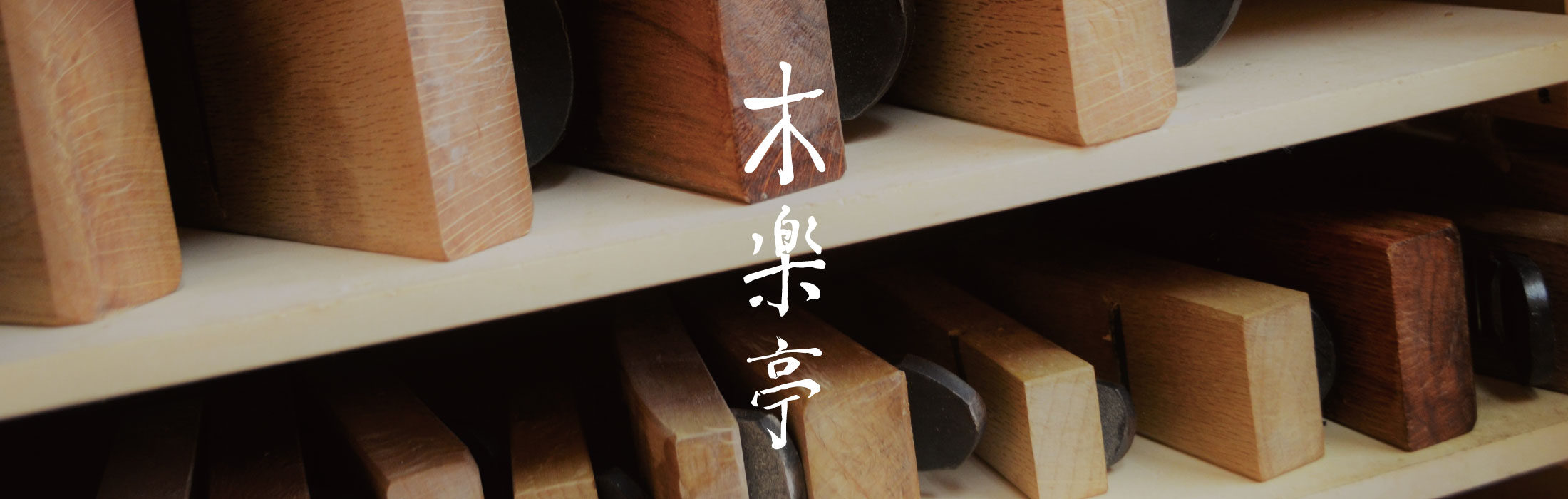こないだの網代の「文庫」が染め上がってきました。
ちょっと赤っぽすぎますね。何より形に締りがありません。蓋の方の「甲盛り」のカーブが深すぎて、蓋ばかりが目立ってしまってます。
籐飾りもまだまだです。連続するカガリ模様の均一さに不満があります。
籐飾りは締めすぎると籐が切れてしまうし、緩すぎると散漫な印象になります。きつすぎず、緩すぎず、すべての力加減が均一になっていなければ仕上がりが満足するものになりません。
習熟するには経験を積む以外にはないようです。

蜘蛛の巣底の花籠2号も染め上がり。
前回のが30点、今回のは65点ぐらいでしょうかね。まだ不満なところはありますが、この花籠はこれで卒業って事にしておきます。

不満が残った巾着籠と文庫の2作目が編みあがりました。
巾着籠の方は、同部分にぐるっと一回りしている桝形模様を、1作目では9本立てにしてしまい、少し貧弱に見えたのと、何より籐飾りが不均一で見るも無残だったのが不満でした。
文庫の方は前述通り。全体に締りの無いコロンとした、散漫な印象だった点です。

2つを並べてみるとよくわかりますが、右の2作目の方が圧倒的に均整がとれています。何よりシャープです。

掛け虫編みっていう連続模様が、どことなく緩んでいる様で、しかも均一性がありません。上の3つ編みのかがりは編み方を間違えています。

掛け虫編みがきちっと締まっているのをお分かりいただけるでしょうか。3つ編みのかがりも正しくできています。
普通はこういう部分はしげしげと眺める訳では無いんでしょうが、「どことなく印象が散漫だなあ。」っていう風に感じられてしまいます。それこそが肝心なところなんですね。

蓋の中央部にちょっと芸をしてみました。今回は9本立ての桝型模様4個ですが、13本建てでもできる事がわかっています。
5mmマスのプロジェクトペーパーに模式図を描いておけば、任意の位置に任意の模様を入れる事が出来るようです。
網代編みは、基本的に編み方自体は単純な繰り返しになるので、勘所さえ掴んでしまえば「簡単」なのですが、その分全体のフォルムに対する敏感な感受性が仕上がりを大きく左右するようです。
渡辺勝軒斎っていう網代の神様(故人)みたいな人がいて、ティファニーに頼まれて小さな手持ちのハンドバッグを作っていて、何とも言えない色気のあるフォルムなんで、あこがれています。
来月からこのバッグをコピーしてやろうと思っています。
何しろ、世界中の店舗に最低1個は置きたいと言われたのに、1か月に1個で年間12個、それ以上は作らないって言ったそうです。何とか言う女優が椅子の上に置いていたのに座って壊したとかで、それだけは追加で作ったって言うんですが、壊れたのも入れて13個しか無いっていう代物です。
ワクワクするなあ・・・・・。
今の処暫く(4~5年)は網代だけを専攻してみようと思う今日この頃でございます。
終わり。